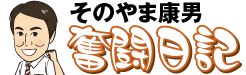

兵庫県宝塚市「フレミラ宝塚」は、老人福祉センターと大型児童センターの複合施設で、高齢者と児童に「学習・文化活動」「仲間づくり」「交流」の場を提供します。「フレミラ」の名称は、ふれあいとみらいを築く世代間交流の拠点を目指し、一般公募で決められました。施設の運営は宝塚市が社会福祉協議会に委託しており、12名の職員で管理しています。利用時間帯を平日の午前9時から午後5時までは老人福祉センター優先とし、午後5時から午後9時までと土曜日、日曜日、祝祭日は大型児童センターを優先とする「タイムシェアリング」により、2つの施設がうまく機能しています。また、となりに大きなスーパーマーケットがあり、買い物ついでに施設利用ができ、特に駐車場がいっぱいの時は利用者に便利で、乳幼児連れの親子は自動車で市内の遠方からも訪れるとの事でした。

今回の委員会視察と重なってしまい、残念ながら大平市民センターの「環境を話し合う会」は欠席させていただきました。 兵庫県姫路市「すこやかセンター」は市民の健康づくり、高齢者の生きがいづくり、子育ての支援という3つの機能を持つ、高齢者から子どもまで幅広い世代の保健・福祉ニーズに対応できる福祉施設です。1階が健康づくり施設(温水プール、トレーニングルーム、運動フロア、リラクゼーションルームなど市民が各自の年齢や体力に応じて気軽に健康づくりに取り組める施設)、2階が老人福祉センター(ホール、和室、集会室など高齢者の生きがいづくり・仲間づくりの場として利用できる施設)、3階が子育て支援施設(情報相談、ファミリーサポート、子育て学習など子育てに関する支援事業を行う施設)になっています。また、この施設は太陽光発電装置を設置し施設内のエネルギーに利用したり、雨水や地下水を植木の散水やトイレ用水に活用し、環境にも配慮しています。岡崎市に建設予定の(仮称)岡崎げんき館によく似た施設で、1階の有料施設の利用者数が気になりましたが、市内の民間業者とは違い、60歳以上の定期利用券購入の割合が多く、年間156468人(開館日数308日 1日平均508人)で順調との事でした。

岡崎市・額田町合併記念式典 平成18年新年交礼会に出席しました。この合併で、人口約37万人(県内5位) 面積387.24k㎡(県内3位)の新「岡崎市」が誕生しました。本市はこれから、三河の中心的都市として、重厚な文化、伝統を持つ都市地域と、豊かな水と緑を持つ山村地域が一体となった「人、水、緑が輝く 活気に満ちた 美しい都市 岡崎」を目指します。 また、今年は7月1日に市制90周年を迎えます。4月からは本市を舞台にしたNHK連続テレビ小説「純情きらり」が始まり、全国に岡崎の名が発信され、今から放映が楽しみです(この放映を起爆剤として官民ともになって観光客の獲得に力を入れたいところです)。 さらに時期は未定ですが乗用車のご当地ナンバーの導入がきまり、導入後は「三河」ナンバーから、新規登録時や番号変更時に自動的に「岡崎」ナンバーになります(三河ナンバーでも希望しナンバープレート代を支払えば岡崎ナンバーに変更できます)。 今後、ますます話題にあふれ、活気のある新岡崎市にしたいと思いました。
岡崎市は、市が管理する13小学校などの公共施設24棟でアスベスト(石綿)が使用されていることを発表しました。 今回の判明分のうち、多数の出入りがある建物(13棟)として、美術館展示室、根石小学校、男川小学校、美合小学校、三島小学校、愛宕小学校、秦梨小学校、藤川小学校、緑丘小学校、六ツ美北部小学校、六ツ美南部小学校、生平小学校、竜谷小学校の校舎の梁や階段裏などで、機械室など特定の人だけが出入りする建物(11棟)として、市役所本館、市役所北館、繊維センター廃水処理場、合歓木排水機場、東部学校給食センター調理棟、東部学校給食センターボイラー室、東部学校給食センター車庫、東部学校給食センター倉庫、北部学校給食センター汚水処理場、図書館機械室、常盤小学校ブロアー室の天井や内壁などです。 この他、現在使用の有無が判明していない建物(2棟)、市竜美丘健診センターと少年自然の家は分析中です。 今後の方針として、多数の出入りがある建物は順次計画的に除去、封じ込め等の工事を行い、対策工事に着手する前においては、飛散の有無の確認のため環境調査を定期的に実施し、飛散が認められた時は閉鎖も検討します。また、機械室など特定の人だけが出入りする建物は囲い込み、封じ込め、除去を検討するとの事です。
