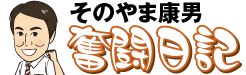
担当する経済建設委員会が開会され 委員会に付託された議案(平成20年度岡崎市一般会計予算も含)対し質疑・採決しました 労働費では雇用対策としてニートと呼ばれる失業・無業状態にある若年求職者の就職自立支援や子供の就職に悩む保護者に個別相談がなされます 農林業費では原油価格の高騰により経営を圧迫されている施設園芸農家(ナス イチゴなどの施設園芸農家・観葉植物 洋ランなどの花き温室農家)に緊急支援がなされます 商工費では城下舟遊びに昨年の「竹千代丸」のほかに新たに「元康丸」が加わります また 家康行列には琴光喜関の参加を呼びかけ親方や本人の感触もよかったようですが春の巡業と重なり残念ながら不参加となりました 土木費では引き続き 道路橋りょう・河川・公園など整備事業がなされます 来週は福祉病院委員会 環境教育委員会 総務企画委員会と順次開会です あっ! 今日は私の誕生日でした プレゼントは「おめでとう」の一言でいいんですよ
